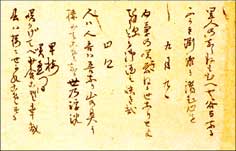
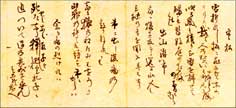
里人のしらぬもむべや谷間なる
ふかき渕瀬に潜む心を
九月九日
白菊の咲き栄ぬる世なりせば
手に取る杯も快き哉
山郷
人は人吾は吾なり
山の奥に棲てこそしれ世の浮沈
早梅
咲がけて咲みつるこそ幸哉
春は梅にせかされこそする
寒松
雪折れし松に罪こそなかりけり
栽にし人のむくいなるらん
吹く風に積りし雪を払せて
緑もかわらぬ庭の松枝
山を出て市に遊ぶ
志々猿を友とし送る山人も
三味の音を聞く耳はあり
市に出し後、病の起りぬれば
志々猿のねたみはをろか山神の
許しも待ず市に出しは
余り病の烈ければ
死んだなら釈迦と孔子に追ついて
道の奥義を尋んとこそ思へ
|| △ ||
【自ら笑う】
人生は元一夢。須べからく逸豪の楽しみを尽くすべし。
自ら笑う我が心拙にして。終身腐儒をまなぶ。
これは安政年間の作と思われているものです。
晋作はこの作が気に入っていたらしい。
扇面に書き付けて、同士の品川弥二郎に贈ったものが現存する。
晋作がまだ若くて松下村塾にも通っていないころの作ではないでしょうか。
安政といえばあの安政の大獄のあった時代ですね。
【焦心録後に題す】
内憂外患我が州に迫る。正に是れ危急存亡の秋。
唯邦君のため邦国のため。降弾名姓また何ぞ愁えん。
元治元年後半の作であるという。
第一次長州征伐と外国の連合艦隊に破れてまさに長州は危急存亡の時でした。
第二次長州征伐もはじまり、晋作が功山寺で決起するすこし前のころのものでしょうか。
これは詩吟などでもっともよく吟じられている七言絶句であるという。
【題不明】
風塵の際を脱出し。酒瓶只自ら親しむ。
酔来りて肘を枕に眠る。識らず何人をか夢見る。
慶応元年暮れに作られたと思われる作。
晋作はこの作に大分自信があったらしく自画像に賛として書き加えたり同志の福田侠平に贈っているという。
この時期は幕府との四境戦争の前年にあたります。
国事奔走に疲れていたらしいとのことです。
【題不明】
廟堂原野評論を解く、勇功と智名とを称歎す、
勝ち易きに勝つは孫呉の術、秋豪名月は是れ精兵
慶応2年4境戦争の勝利後につくられたもの。
晋作は当時、すでに結核が悪化し、病床にあった。
起句の廟堂は官の意味で原野は民の意味です。
この詩は勝ち戦さにうかれた長州を醒めた目で自戒したものだそうです。
【上海行きに際して】
断然命を奉じて雲津に入る 国のため身を忘る
敢えて人に譲らず 只 恨むらくは我に兄弟の
乏しく 欠如す膝下 双親を慰むるを
文久2年(1862年)晋作が上海に行く前年に渡航のことが決まったとき詠まれたもの。
晋作は上海行きを喜んでいたが、それは同時に当時としては命がけのことであり、両親に対する孝心が表れているようです。
【囚中作】
身は棲禽に似て繋囚となる 心は逝く水の如く悠々に付す
夜来独り怪しむ孤床の上 魂は走り夢は迷う六十州
脱藩の罪で野山獄にあった元治元年の作である
この獄中にいるとき晋作は集中的に詩を作ったという。
かなり悶々としていたらしい。
【鈴鹿山】
喬木陰森古関暗し 英雄賊を挫く是斯の間
へい衣弧剣客中に老ゆ 秋雨重ねて過ぐ鈴鹿山
晋作が始めて江戸に遊学する途中で詠んだ詩です。
雨に煙る東海道の難所、鈴鹿山を通るときの詩です。
このときの晋作はまだ、志士の晋作ではなかったでしょう。
翼あらば千里の外も飛びめぐり
よろずの国を見んとしぞ思う
上海行きを命じられる二年ほど前に江戸で昌平坂の学問所などで勉強していたころ、品川弥二郎あての手紙に書かれたものです。
当時の若者は海外に惹かれていたことがわかるような気がします。
灯火の影細く見る今宵かな
俗論党が政権をにぎり、晋作が一時九州へ逃れるとき書き残したものです。
奇兵隊をあとにして九州で義兵を募るために出発するときの悲壮な気分をあらわしているのでしょうか。
藩を倒幕路線へと変えた慶応元年の八月六日、桜山招魂社ができあがった。
晋作が前の年から建策し白石正一郎らが世話人となって、奇兵隊員らが手伝って完成したものである。
下関新地岡ノ原につくられたわが国最初のものである。
このときの晋作の奉納歌が次のものである。
弔わる人に入るべき身なりしに弔う人となるぞはずかし
この年の間に薩長同盟が成立し、幕長戦争がまもなく始まろうとしていました。
幕末の動乱の中で落命した草莽の人たちへの晋作の心遣いが感じられます。
また後日次の和歌も作っています。
おくれてもおくれても又君たちに誓いし言を吾忘れめや
晋作は彼の死の直前に彼の父の小忠太へ歌を送っている。
慶応二年暮れのことである。
人は人吾は吾なり山の奥に棲みてこそしれ世の浮き沈み
うぬぼれて世は済みにけり歳の晩
当時晋作は下関の桜山招魂社の見える丘の小さな家を借りて療養していた。
そして年があけて新地林算九郎宅の離れ座敷に移りそこで最期を迎えた。
最初の歌は晋作のもはや再起不能と自ら覚悟した無念の気持ちが現れているような気がします。
(本文、詩・和歌:藤井 氏提供)
|| △ ||

